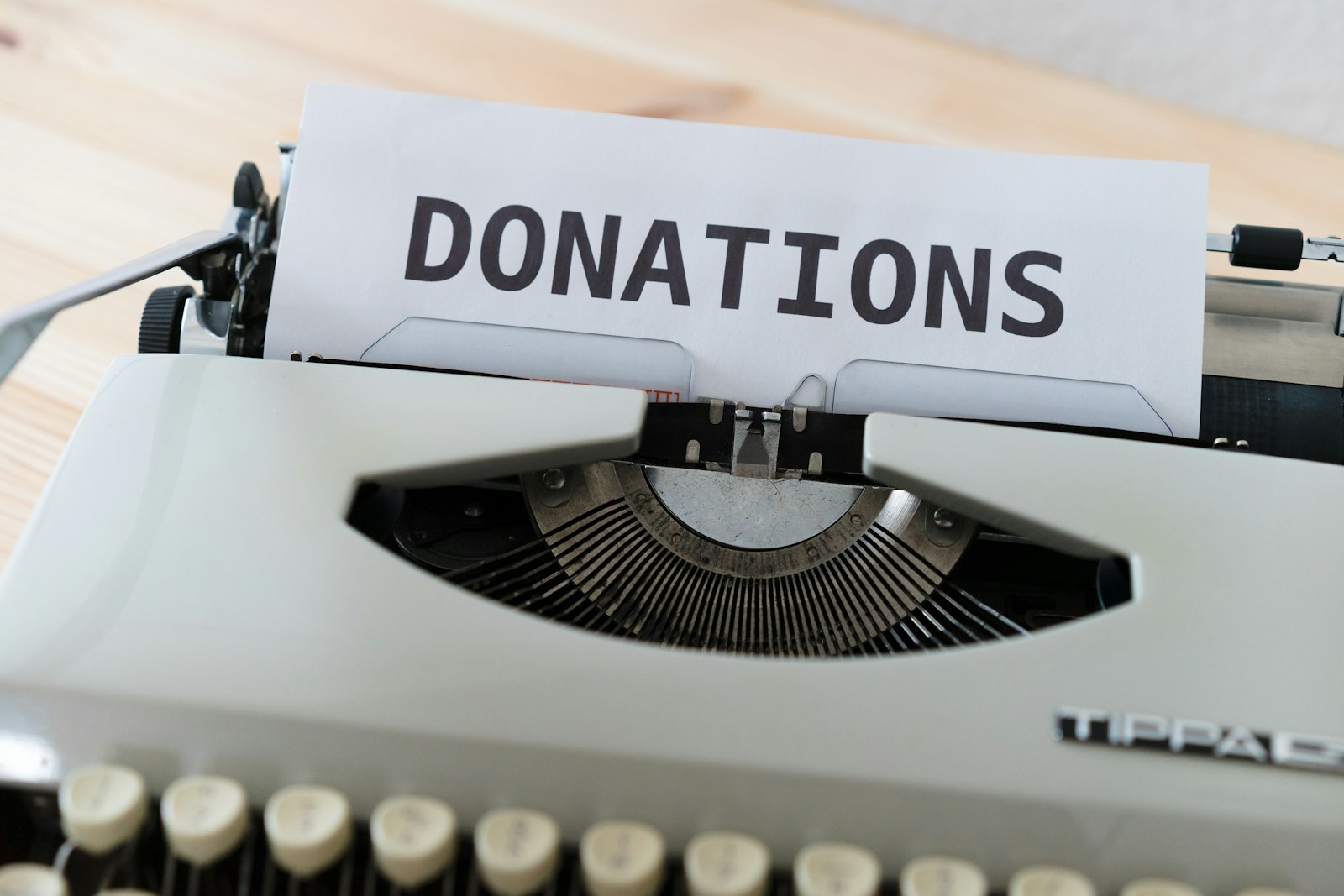日本経済の持続的な成長と国際競争力の回復は、国家的な最重要課題である。その根本的なドライバーが、新しい産業や価値を生み出すイノベーションであり、その源泉こそが大学や公的研究機関における「研究力」にほかならない。
しかし、主要国との研究力競争において、日本の地位は相対的に低下し続けている。この地盤沈下の背景には、公的資金の削減や硬直化による研究環境の悪化がある。
この閉塞状況を打破し、研究現場に自由と活力を取り戻す鍵として、今、「寄付金」の持つ戦略的価値がかつてなく高まっている。本稿では、寄付文化の醸成がなぜ日本の未来への最良の投資となるのかを、その資金特性から論じたい。
経済成長のエンジン「研究力」の危機的状況
イノベーションが経済成長の源泉であることは論を俟たない。そして、そのイノベーションの「種」となる基礎研究や、社会実装へとつなぐ応用研究の多くは、大学で生まれている。
かつて技術立国として世界をリードした日本の研究力は、近年、論文の質・量双方の国際比較において苦戦を強いられている。その背景には、基盤的経費である運営費交付金の削減、それによる若手研究者ポストの減少、研究時間の圧迫といった構造的な問題が横たわっている。
研究者が自由に、大胆に挑戦できる環境の整備は不可欠だが、現状の財政基盤はそれを許容し難い状況にある。
公的資金の壁ー「単年度主義」と「使途の硬直性」
大学の主要な財源である運営費交付金や競争的資金は、その性格上、厳格な制約を伴う。予算管理の現場では、これらの資金が**「単年度での予算執行(使い切り)」を原則とし、「厳格な費目(使途)の制限」**に縛られていることが、研究の自由度を阻害する大きな要因となっている。
例えば、年度末に予算を使い切るための調整や、申請計画時に想定していなかった有望な研究テーマへ迅速にリソースを振り分けることの困難さは、多くの研究者が直面する現実である。
このような硬直的な資金運用は、長期的な視点に立った研究計画や、失敗を恐れない挑戦的な研究(ハイリスク・ハイリターン研究)の推進とは、残念ながら相性が良いとは言えない。
寄付金が持つ「戦略的柔軟性」という真価
これに対し、寄付金、特に使途を特定しない一般寄付は、他の資金源にはない圧倒的な**「柔軟性」**を提供する。この「使いやすさ」こそが、日本の研究環境に決定的に不足している要素である。
- 長期的・計画的投資の実現: 寄付金は、原則として年度を超えた繰り越しが自由である。これにより、高額な最先端機器の計画的な導入や、優秀な研究者・技術支援者を複数年にわたり安定的に雇用するなど、単年度主義の壁を超えた中長期的な研究戦略の実行が可能となる。
- 創造性と萌芽的研究への投資: 公的資金の審査では評価されにくい、独創的すぎるアイデアや、成果が出るか不透明な萌芽的研究への「種銭」として機能する。また、研究の途上で予期せぬ発見があった際、迅速に研究の方向転換(ピボット)を行うための機動的な資金としても活用できる。
- 研究基盤(インフラ)の抜本的強化: 老朽化した施設・設備の改修、研究者の事務作業を軽減するURA(ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター)の配置拡充など、研究活動の土台そのものを底上げする投資にも、大学の裁量で柔軟に充当できる。
この「戦略的柔軟性」こそが、硬直化した研究資金システムにダイナミズムをもたらし、研究者の創造性を解き放つための触媒となる。
「未来への投資」としての寄付文化をどう醸成するか
この柔軟な資金を社会全体で育てていくためには、寄付を単なる「慈善活動」ではなく、**「社会全体が未来の成長のために行う合理的・戦略的な投資」**と捉えるマインドセットへの転換が不可欠である。
その醸成には、資金を受け取る大学・研究者側と、社会・制度側の双方の努力が求められる。
- 大学・研究者側の責務(アカウンタビリティ): 研究者は、自らの研究が社会にどのような価値をもたらすのかを、クラウドファンディングなども活用しながら積極的に発信する必要がある。同時に、受け取った寄付金がどのように使われ、どのような成果(たとえ失敗であったとしても、その知見)に繋がったのかを透明性高く報告し、寄付者との信頼関係を構築する責任がある。
- 社会・制度的支援: 個人や企業が寄付を行いやすくするための税制優遇措置のさらなる拡充と、その認知度向上が急務である。また、寄付者と研究者を繋ぎ、長期的な関係性を構築する専門人材(プロのファンドレイザー)の育成と大学への配置も、欧米に比べて立ち遅れている分野であり、強化が必要だ。
結論
日本の研究力を再興し、経済成長の軌道に戻すためには、公的資金の拡充と並行して、民間の活力を取り込む「寄付」という名の柔軟な資金源の確立が不可欠である。
寄付金の持つ「柔軟性」をテコに、研究現場の自由度と創造性を最大化すること。そして、公的資金、企業との共同研究、そして寄付という多様な資金が有機的に機能する研究エコシステムを構築すること。それこそが、イノベーションを絶え間なく生み出し、日本の持続的成長を実現する最も確かな道筋であろう。